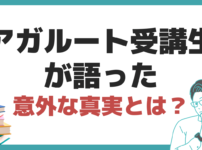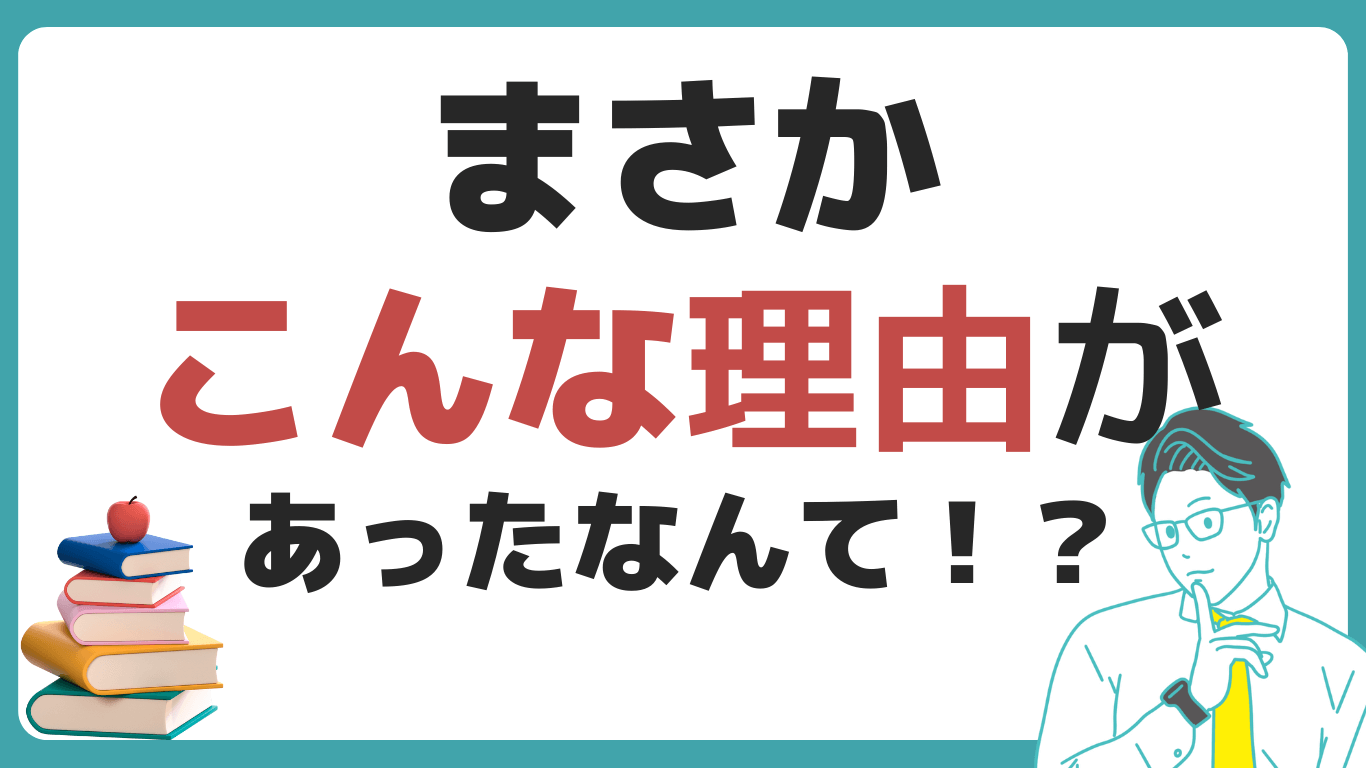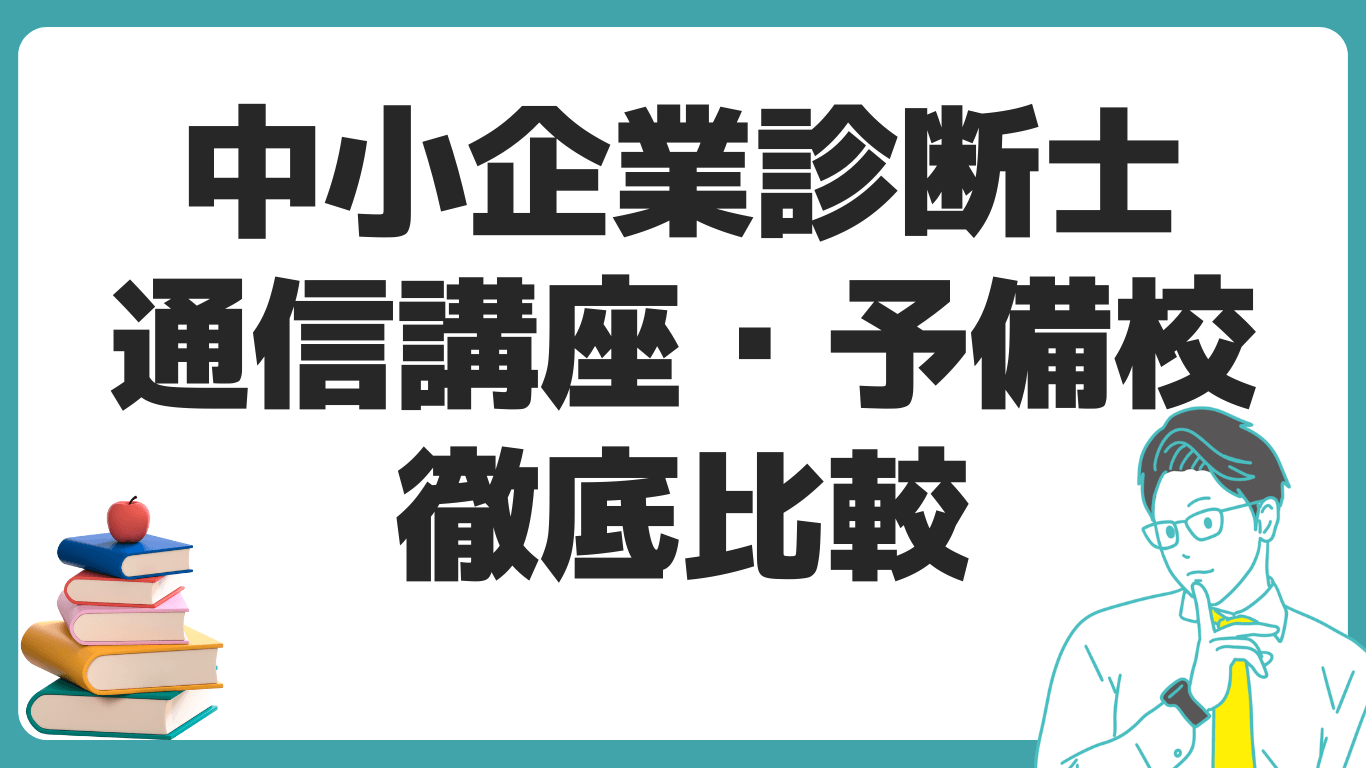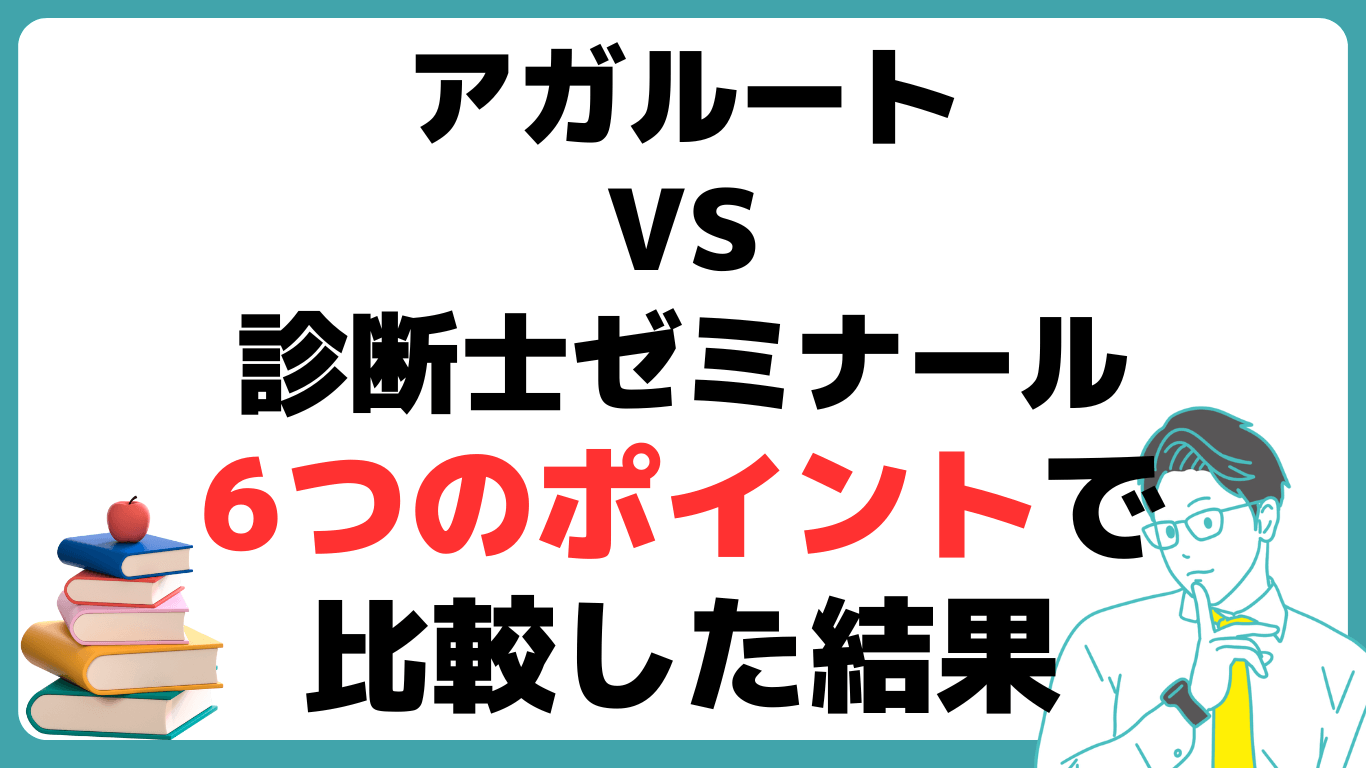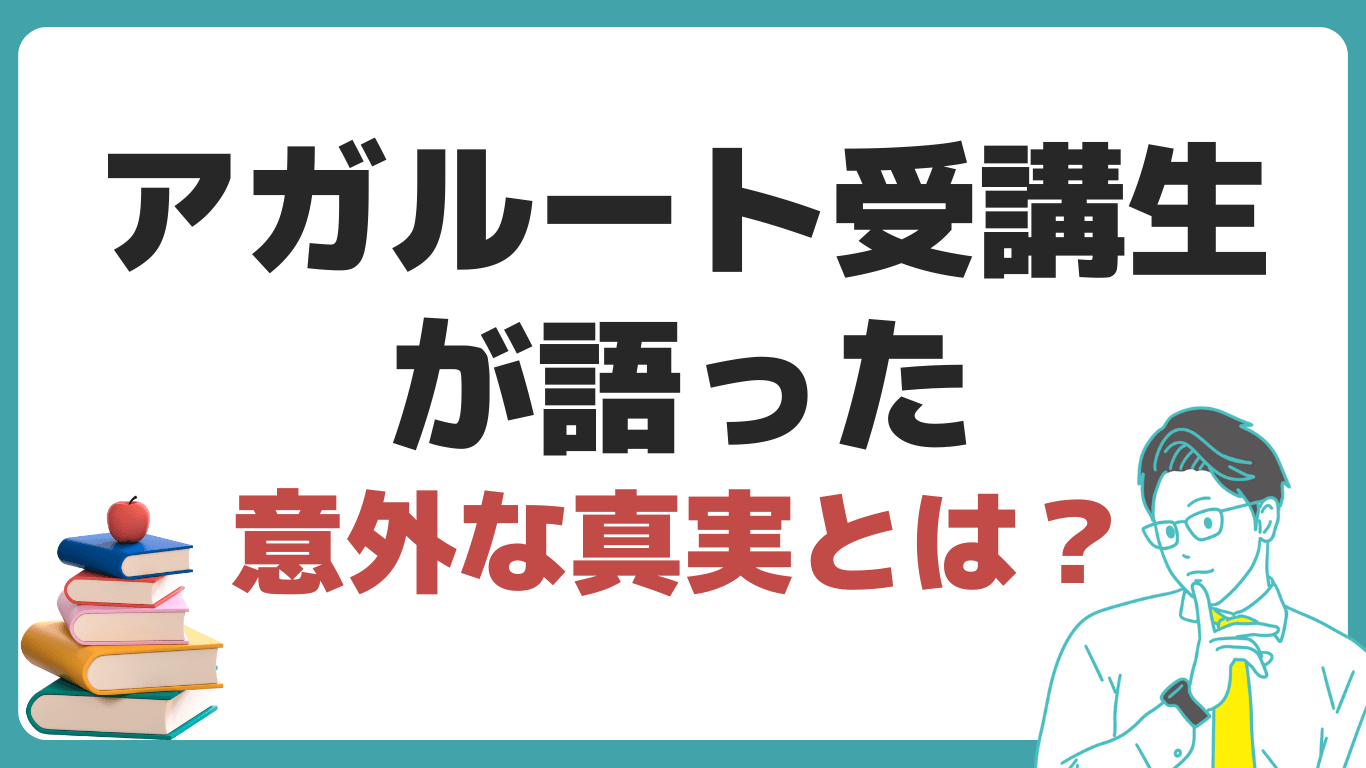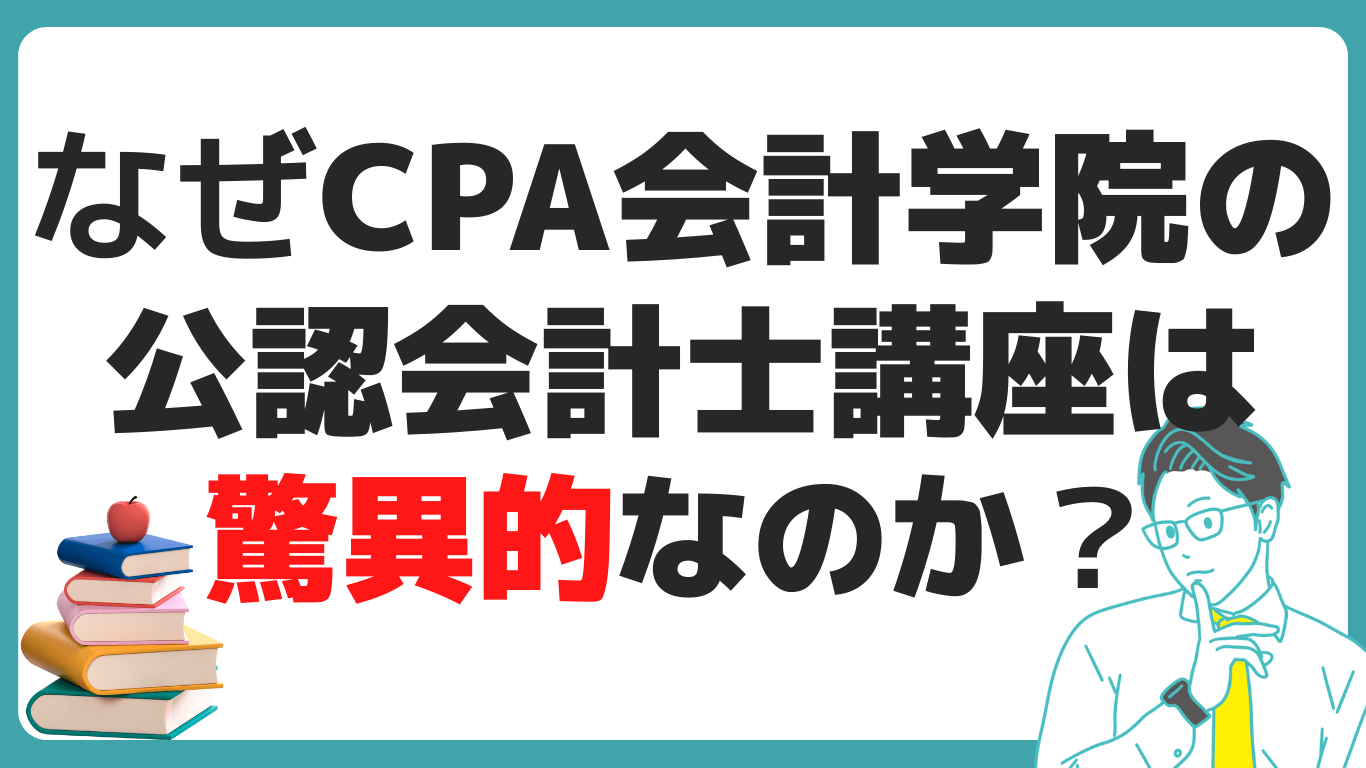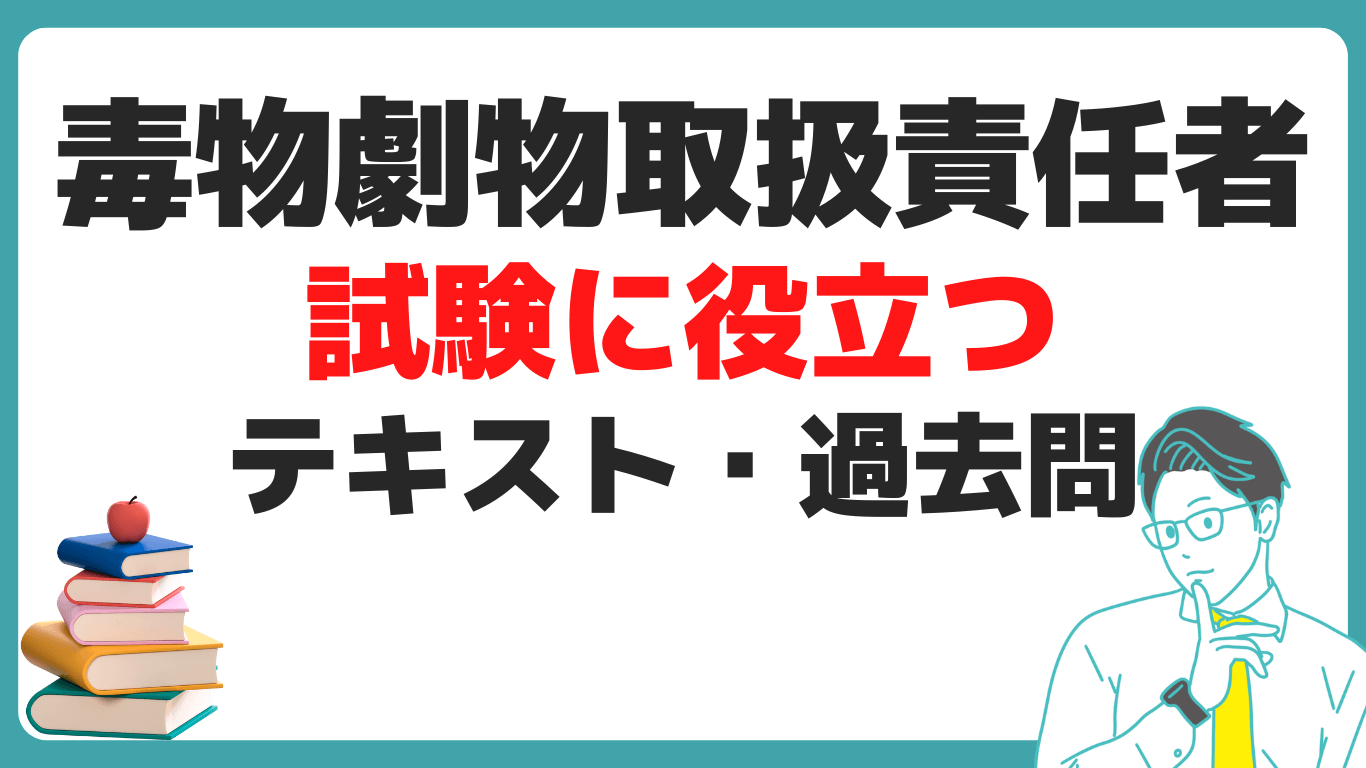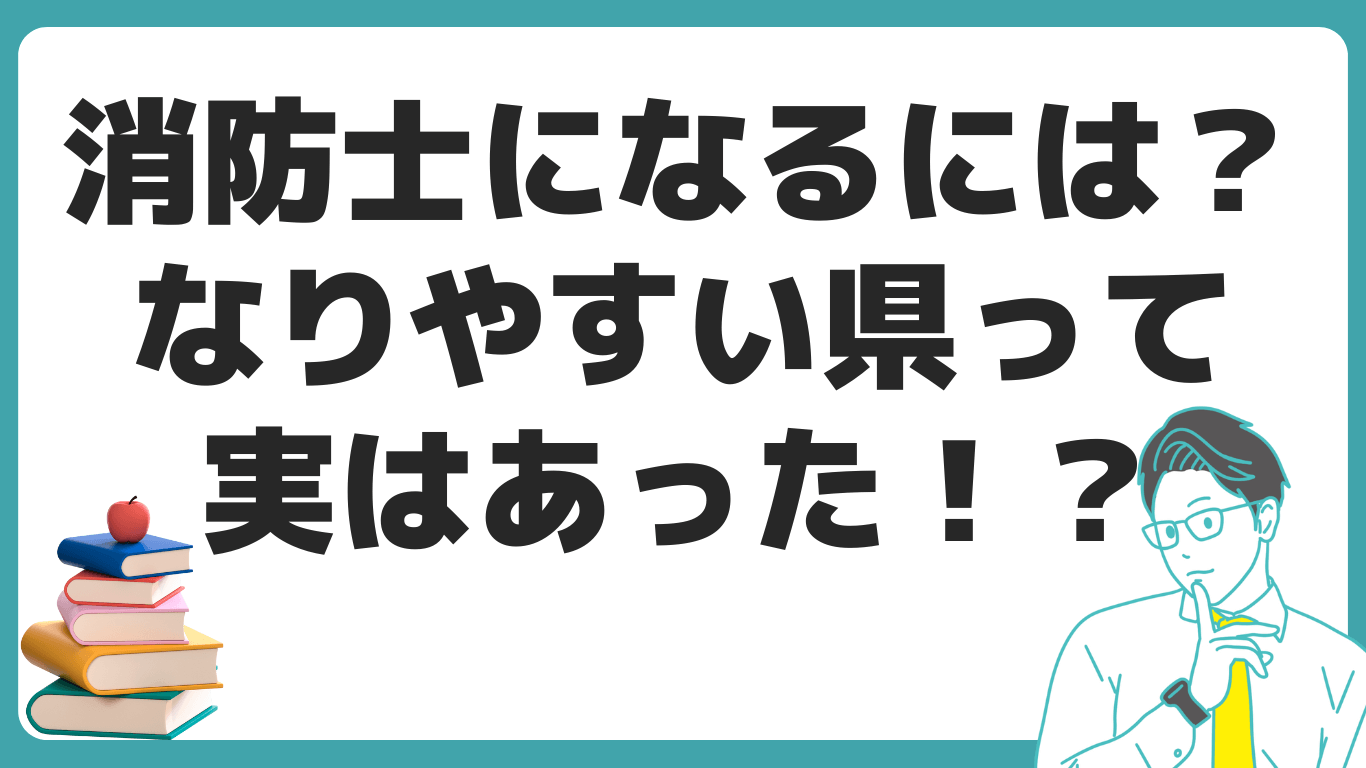救命救急士の資格が就職・転職に役立つのか、またこの資格の活かし方や、収入と将来性、合格率、おすすめテキスト、参考書や問題集などを解説していきます。
結論として、救急救命士の資格を取得したとしても、各自治体の消防職員(消防士)採用試験に合格して消防の救急隊員にならなければ資格を活かすことはできません。
消防官の採用試験に強いおすすめ講座について解説しています!
上記の内容について解説していきます。
合わせて読みたい
アガルート やばい 評判なのに国家試験の合格率の高さの秘密とは?
アガルート やばい!? 国家試験の合格率の高さと評判の秘密とは?
早速SNS上の口コミを見ていきましょう! アガルートのテキスト分かりやすい😆他資格セレクト問題もローラー的な聞き方で結びつけやすい! — Taka@yokohama (@6GG9IpivuHZ1JdK) March 13, 2021 アガルートの入門講座を受講。いろんなサンプル講座聴いた中で豊村先生の声が1番相性良かった☺️わかりやすいとの声も多かったので楽しみ😊 — ぱんだちゃん@行政書士R5受験生 (@panda88gyousei) Sept ...
救命救急士とは?

救急救命士は、病気や怪我などの急病患者を緊急で病院に搬送する際に、救急車の中で生命を維持する措置を行うのが主な仕事です。
大量の失血があった場合などは、病院に着くまでの処置で患者の生死が分かれます。
救急救命士は、止血処置や脈拍の測定はもちろんのこと、心臓や呼吸の止まっている患者に対して、医師の指示を受けながら点滴や気道の確保などの救急医療行為もおこないます。
救急救命士の活躍の場は主に救急車です。
患者を搬送する際に救急車に搭乗して、病院に到着するまでの限られた時間内に医療行為をして人の命を救います。
あくまでも病院に着くまでの間です。
救急救命士は病院内では医療行為はできません。
病院で医療行為をするのは医師や看護師です。
救命救急士になるには?

救急救命士になる手段は、大きく分けて2通りです。
- 民間の救急救命士を養成する専門学校・短大・大学において受験資格を得る。
- 消防の職員(消防士)として採用された後に、養成所に通って受験資格を得る。
いずれも定められた過程を修了すれば受験資格を得られるだけですから、その後国家資格に合格しなければなりません。
1.の場合は、最短で2年間学習して試験に合格すれば救急救命士になれます。
もちろん学費などは自己負担です。
大学であれば4年生の3月に国家試験を受験し、救急救命士の資格は取得見込みとしてその後各地方の採用試験を受けます。
2.の場合は、消防士として就職してから、厚生労働省令で定める課程を修了(250時間)し、その後、5年または2,000時間の実務経験を経た後、6ヶ月以上の救急救命士養成所で研修し受験資格を得ます。
税金を使って専門の過程を学習するので、大学や専門学校のように学費はかかりません。
消防士全員が救急救命士になるわけではないので、該当する部署に異動にならない限り機会はありません。
勤務評定にもよりますし、自治体によっては選考試験もあります。
しかも、一定以上の救急の経験がないと養成所すら入れませんので取得までに時間がかかります。
自治体の方針や所属部署にもよりますが、早くても6年以上、中には10年以上かかるところもあります。
もちろん大学・専門学校を卒業と同時に救急救命士の資格を取得して、そのまま消防士として就職する人も大勢います。
これが救急救命士の資格を最も活かせる可能性の高い進路かもしれません。
一部ですが、自衛隊や海上保安庁、警察でも資格を活かした仕事をするのは可能ですが、一般的ではないです。
救命救急士資格の活かし方

救急救命士の資格を取得すれば、必ずその資格を活かせる職業に就けるわけではありません。
救急救命士は単なる資格でしかないということです。
救急救命士の資格を活かせる職業は現時点ではほぼ消防士に限られています。
病院やその他の医療施設では役立つ資格ではありません。
消防士になる覚悟が無ければ将来性もなく、取得しても役に立たない資格といえます。
救急救命士の資格を取得すれば消防士として採用されるのではなく、取得した後に消防士採用試験(公務員試験)を受けて合格しなければなりません。
仮に大学・専門学校を卒業して救急救命士の資格を取ったところで、消防士にならなければ学費と費やした時間が無駄になってしまいます。
高校を卒業してから入学する救急救命士になるための専門学校も増えていますが、卒業生全員が消防に就職できて救急救命士として働ける状態ではありません。
救急救命士の資格を取得しても、消防士になれるのは30%とも40%とも言われています。
もちろん最初から採用試験をあきらめている人もいますから、卒業生全体で見るとさらに消防士になる確立は低いと思われます。
高校を卒業して、救急救命士の専門学校へ進もうと考えているのであれば、自分が進もうと考えている大学や専門学校の消防士就職率は何パーセントぐらいか、よーく調べてその上で判断してください。
本当は消防士として就職し、それから現場での経験を重ねた上で職務上救急救命士を目指すのが一番良い方法ともいえます。
そうすれば救急救命士の資格が無駄になることはありません。
救命救急士の将来性

資格を持っているから就職できるわけではなく、あくまでも消防士として公務員試験に合格してから活かせる資格です。
大学や専門学校で救急救命士の学習をするのであれば、同時に公務員試験対策の学習もしなければなりません。
そして、国家試験に合格して、その後採用試験にも合格してはじめて活かされる資格です。
消防士になれず病院で働く救急救命士は多い
消防士として就職できない(採用試験に不合格)ため、来年以降の合格を目指して浪人(消防浪人)しながら病院で働く救急救命士もいます。
しかし、救急救命士とはいえ病院で医療行為はおこなえません。
病院では救急救命士の資格は紙切れ同然なので結局何もできず、業務の内容は資格が要らない看護助手と同じだったりします。
つまり看護師の雑用です。
資格があったら消防士の採用に有利?
救急救命士の資格を取得していれば、消防士の採用試験は有利になるのではないか?
って思いますよね。
あらかじめ資格を持っていれば、後から税金を使って研修に行かせる手間も省けるはずです。
しかし現実は違います。
救急救命士の資格を持っていても有利にはなりません。
全国ほぼどこの救急隊にも必ず最低1名は救急救命士がいます。
2名や救急隊3名全員が救急救命士なんてことも珍しくありません。
つまり、救急救命士の数は足りていてこれ以上の需要は無く、新たに採用する必要がないんです。
万が一必要であれば、税金を使って職員を養成所へ行かせれば済むことです。
残念ながら、有資格者であっても公務員試験は有利にはなりません。
合わせて読みたい
消防士になるには?消防士になりやすい県ってあるの?
おすすめ「公務員【消防士向け】予備校」は、以下になります。 ランキング 予備校 第1位 LEC 第2位 資格の大原 第3位 EYE公務員試験予備校 第4位 クレアール 第5位 資格の大栄 上記ランキングの詳細記事は、下記になります。 【消防官向け】公務員試験予備校は、ズバリこの5校!! アガルート やばい 評判なのに国家試験の合格率の高さの秘密とは? 消防士になりやすい県とは? 消防士になりやすい県を1から探すのには苦労するかと思います。 ここでは、J-LIS地方公共団体情報システム機構を利用し、全国にど ...
救急救命士と看護師、どっちがおすすめ?
人を助けられる職業に就きたい、ということで救急救命士か看護師のどちらかを目指したいと考えている人もいるようです。
特に女性です。
どちらでもかまわないのであれば、看護師の方が堅実だと思います。
救急救命士の資格を取得しても、採用試験に受からなければほぼ役に立ちません。
仮に採用されたとしても、救急救命士の数は足りている場合も多く、すぐに救急隊へ配属されるとは限りません。
看護師の場合、学校に通い国家試験に合格すれば100%看護師として病院に勤められます。
資格取得後から早期に医療の現場で働けます。
また看護師は全国的に不足しているので就職先には困りませんし、転職も比較的自由にできます。
一方、救急救命士の活躍の場は救急車の中に限られるため就職先も消防関連に限定されます。
救急救命士か看護師で迷っているのであれば、看護師の方がおすすめです。
将来性もあれば、需要もあります。取得するメリットは段違いです。
看護師(認定看護師)と救急救命士、両方の資格を取得する人も増えています。
合わせて読みたい
看護師になるには大学進学と専門学校どっちがおすすめ?
上記の内容について解説していきます。 関連記事:アガルート やばい 評判なのに国家試験の合格率の高さの秘密とは? 看護師とは? 医師の右腕として医療の現場で大活躍する看護師。 夜勤や三交代制などがあるハードワークとしても知られ、理想と現実のギャップに悩まされやすい職場でもありますが、それだけに非常にやりがいのあるお仕事であり、特に女性にとっては、あこがれの職業であり続けています。 医療機関にて患者のケアや診療のサポートをおこなうスタイルが代表的ですが、社会福祉施設や訪問看護ステーションなど、スキルを発揮す ...
救命救急士試験合格率

救命救急士試験の受験者数と合格率は以下になります。
| 実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2021年 | 2,999人 | 2,599人 | 86.7% |
| 2020年 | 2,960人 | 2,575人 | 87% |
| 2019年 | 3,105人 | 2,854人 | 91.9% |
| 2018年 | 3,015人 | 2,562人 | 85% |
| 2017年 | 3,031人 | 2,576人 | 85% |
救命救急士試験おすすめテキスト・過去問【PR】








救命救急士試験概要
救命救急士試験概要は以下になります。
| ホームページ・ 受験申込・問合せ | 厚生労働省 |
| 受験資格 | 大学入学有資格者で、指定救急救命士学校・ 養成所(2年制)を卒業した者。 大学で1年以上公衆衛生学等13科目 を修了し、指定校で1年課程の修了者。 医大等で公衆衛生学、 臨床実習等を修了した者。 所定救急業務講習を修了し、5年又は2,000時間以上 就業し、指定校で1年課程を修了した者。 外国で救急救命士学校卒業、又は、有資格者で 1.2.3.4.と同等以上と認定された者。 看護婦(士)有資格者で、有資格者で 1.2.3.4.と同等以上と認定された者。 |
| 願書申込み 受付期間 | 1月上旬~下旬頃まで |
| 受験料(税込み) | 30,300円 |
| 試験内容 | ① 基礎医学 ② 臨床救急医学総論 ③ 臨床救急医学各論(一) (臓器器官別臨床医学をいう。) ③ 臨床救急医学各論 (二)(病態別臨床医学をいう。) ③ 臨床救急医学各論 (三)(特殊病態別臨床医学をいう。) |
| 身体上の障害等に係る 特別措置について | 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能に障害を 有する者で受験を希望する者は、指定された日までに 一般財団法人日本救急医療財団に申し出ることで、 受験時に申請した障害の状態に応じて必要な配慮を 講じてもらえることがあります。 |
| 試験日程 | 3月中旬頃 |
| 受験地 | 北海道 東京 愛知 大阪 福岡 |
| 合格基準 | 以下全ての基準を満たした者が、合格となります。 ① 必修問題:満点の80%以上の得点率 ② 通常問題:満点の60%以上の得点率 |
合わせて読みたい
アガルート ひどい 評判だけど実際どうなの!?元受講生に聞いた意外な真実
【最新】アガルート 評判 良い?悪い? 実際どうなの!?元受講生の口コミでわかった意外な真実
アガルートの講座を受講を検討されてる方の不安解消に少しでも役立てば幸いです。 また、記事の後半に「大切なこと」を体験した人から意見を頂戴していますので、是非参考にしてください! インタビューに答えてくださった以下4名の内容を1人ずつ紹介していきます。 アガルート やばい 評判なのに国家試験の合格率の高さの秘密とは? 山本太郎さんあなたの年齢層と受講した講座は何ですか? 30代、土地家屋調査士の講座です。 アガルートの講座を受講する前に比較検討した講座はありますか?比較検討した内容を教えてください 合格率で ...